医工学治療のコンサルティングができる臨床工学技士を育てたい!
医療保健学部 臨床工学科 塚尾 浩 助教

大学病院の救命救急センターや血液浄化部門などで、生命維持管理装置の運用や操作、保守点検などに携わってきた塚尾先生。現在は、血液浄化技術に関する研究をされています。今回は、その研究の詳細や授業での取り組みについてお話しいただきました。

■先生のご研究についてお聞かせください。
今、取り組んでいる研究の中心は、血液浄化技術に関するものです。血液透析といって腎臓が機能しなくなってしまった方に、その機能を補ってくれる人工腎臓を繋いで血液をきれいにする治療があるのですが、そこで用いられる人工腎臓の生体適合性について研究しています。血液透析というのは、患者さんの腕から血液を1分間に約200cc、ポンプで引き出して、その血液を人工腎臓に通して浄化し、きれいになった血液をまた患者さんの身体に戻すという治療です。人工腎臓に血液を通すということは、結局、血液を異物に触れさせることでもあります。血液が異物に触れると、血液が固まったり白血球などが活性化したりと、凝固や免疫機能の異常が生じます。常にそのような環境に血液があると、風邪をひきやすくなったり、血管が傷んだりなどの合併症が出てきます。この治療を始めた人は、現時点では、一生涯続けていかなければなりません。そうすると、この先10年、20年と、血液を異物に触れさせる環境に置くことが、患者さんの長期にわたる予後に何らかの影響を与えているのではないかと、ずっと指摘されてきました。それを何とか改善しようというのが、私の研究になります。具体的には、人工腎臓をどのようにして血液にとってより優しく、より良いものに変えていくか、ということになります。
■今、取り組んでいる具体的な研究例はありますか?
先ほど、血液が異物に触れることで白血球が活性化すると話しましたが、白血球が慢性的な活性を起こした状態にあると、活性酸素を出すということがわかっています。今、それを除去する、あるいは抑えるということを考えています。例えば、人工腎臓の透析膜表面に抗酸化作用のあるビタミンEをコーティングしたものが市場に出ています。メーカーとしては、活性酸素を抑える効果が期待できるということで発売したわけですが、実際、それが触れた血液にどのように作用しているのか、どう効果を上げているのかについては、まだわからないことが多いのです。そこを明らかにしていこうと取り組んでいます。人工腎臓の場合、患者さんが長く使っていくなかで、初めてわかってくることもありますから、そう簡単ではないのです。ですから、なるべく患者さんが使う前に、どういう影響があるのかを把握する手法についても検討していかなければと思っています。
■先生が今の研究テーマと出会ったきっかけは? また、教員になられた経緯とは?
もともと臨床工学技士として大学病院に勤めていたのですが、そのとき、人工透析を受けている患者さんの中に、さっきお話ししたような風邪をひきやすいといった、免疫力低下による症状が表れている方がたくさんいらっしゃいました。人工腎臓という異物に接触した血液がどのように変化するのかを研究することにより、そのような患者さんを何とかできるのではないかと思い、研究しようと大学院へ入ったのです。また、実際に医療現場で働いてみると、工学の知識だけでなく、もっと臨床医学・基礎医学の知識が必要だと痛感したことも大学院に入った動機です。臨床工学技士というと、機械だけを相手にしているように思われがちですが、実際はそうではありません。私が学生の頃は、工学を学ぶことに力を入れていましたが、臨床現場に出てみると、工学と同じくらい臨床医学・基礎医学がわかっていないと、実際の業務はなかなか進まないということが分かりました。当然ですが、単に患者さんに臓器の働きを代行する機械を繋げばよいわけではなく、患者さんの状態に合わせた治療方法の選択、設定や操作が必要になります。それには医師とのディスカッションを通して、治療条件や操作条件を決めていくことが欠かせないのですが、こちらにその知識がなければ医師との会話すら成り立ちません。そこで、医学と工学を十分に理解している臨床工学技士が絶対に必要だと感じ、そういう人材を育てたいと思って教員になったのです。
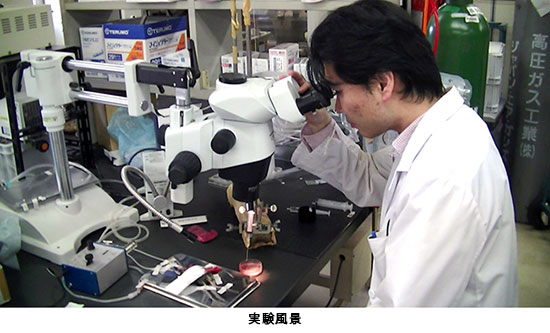
■では、授業ではどういうことを教えていますか?
私が担当しているのは3年生の「血液浄化装置学」になります。この授業では、血液浄化技術全般を扱うので、血液透析や血液ろ過、血液吸着といったことを中心に話していきます。また、肝不全や免疫系疾患に使用する血漿(けっしょう)浄化療法についても扱っています。基本的には、血液浄化の原理などを教えていくのですが、そもそもなぜそういう治療が必要になったかということも含めた臨床的な側面にも触れるようにしています。例えば血液透析は、腎不全患者に施行する治療ですが、腎不全を理解するには腎臓そのものを理解しておく必要があります。そこを理解したうえで原理を学ばないと、臨床現場に出たとき、きちんと患者さんの背景にあるものを理解することができません。実際、臓器の仕組みなどは、1年生の「人体解剖学」で学ぶのですが、この「血液浄化装置学」でも復習を兼ねて触れるようにし、人工臓器と生体の臓器の役割をきちんと頭の中で繋いでもらえるよう、意識して教えています。
また、医療現場で必要となる物理や化学といった理系の知識を学ぶ、1年生対象の「医療科学の基礎」という授業では、物理の実験を少し手伝っています。学生は、こうした理系の基礎的な学びが、臨床現場とは関係ないと思いがちですし、医療系の大学に入ったのだから、すぐに医療の勉強をしたいと思っているとは思います。ただ、この業界は新しい技術が次々と生まれ、今日学んだことが10年後、もっと言えば5年後には陳腐化していることも多々あります。新しい技術が出てきたとき、それを理解するのに何が役立つかというと、実は物理や化学といった基礎の教養なんですよね。ですから、そういう基礎知識が臨床工学の何を理解するために必要かということを教えるようにしています。
■臨床工学技士には、どんな素養が必要だと思いますか?
自分で勉強を続けられることだと思います。今、お話ししたように、臨床現場では新しい技術が次々と出てくるので、自分で勉強を継続できる力は必須になります。そのためにも、大学在学中に勉強の仕方を身につけておくことは、本当に大切だと思います。それに加えて、勉強で得た知識をどのように応用するのかも重要になります。臨床で生じる問題には決まりきった解答なんて一つもありません、むしろ分からないことだらけです。そこが教科書や参考書を探せば答えが出ている受験勉強とは違うところで、むしろ未知の事象を解明する「研究」に近いのかもしれません。ですから、これから臨床現場に出る学生達には研究者の思考で問題解決にあたれる技士になって欲しいと思います。そうすれば、臨床現場において患者さんの背景やこれまでの流れをきちんと踏まえたうえで、現時点で行うベストな治療法を提案できるような人材になれると思います。言われたことだけをするのでなく、背景を理解したうえで、いろいろな提案ができる、つまり医工学治療のコンサルティングができる人材を目指すことが大事だと思います。
■最後に、今後の展望をお聞かせください。
研究では、身体の外に血液を循環させて浄化する人工腎臓を、埋め込み型や携帯型にできないかと考えています。今は再生医療がさかんに取り上げられ、話題ですが、恐らくこれは早くても30年、50年先の技術ではないかと思います。ですから、それが実現するまで既存の技術を発展させ、より高い生体適合性を持つ体に優しい人工臓器の開発に貢献できればと考えています。また、現在では治療対象となっていない様々な疾患、症例に対して血液浄化技術を応用した治療方法の開発を行いたいと考えています。
・次回は5月10日に配信予定です。


