「体幹筋と呼吸の関係を明らかにして、病気の治療に役立てたい」
医療保健学部 理学療法学科 中山 孝 教授

■まずは、理学療法士の役割や目的についてお聞かせください。
理学療法士が目指すところは、ひとりの障害を持った方が、その人らしく暮らす生活の場に戻れるようにする、あるいは仕事を持っている方なら、その職業を再び獲得できるように支援することです。これは実は作業療法士が目指すゴールとも共通しています。そういう意味では、理学療法も作業療法も同じリハビリテーションという位置づけの中にある分野だといえますね。例えば、どちらの職種でも生活環境を調べ、必要あれば家庭訪問をして、どのような工夫や改善が必要かとか、支援に必要な道具を一緒に考えることもします。また、そういう情報を材料にして、逆に病院ではどういう動作を獲得する必要があるだろうかということも考えていきます。
では、理学療法の特徴は何かといいますと、比較的、身体機能面を重視することが挙げられます。基本的な動作、運動を再獲得してもらえるように支援するのです。例えば、関節が硬くなり腕が曲がらないという場合は、その腕を曲げてあげる。それによって患者さんは食事ができるようになったり、その他の腕の活動ができるようになったりするのです。また、歩けない人の場合は、ベッドから起き上がる練習をしたり、座る練習や立つ練習をしたりして、日常の活動に必要となる動作を一緒に行っていきます。ですから、基礎的な動作や運動を一緒になって達成していくことが、理学療法の一部であり、むしろそれが中心ともいえます。理学療法士が専門的に活躍する場としては、整形外科クリニックやスポーツの世界が挙げられます。また、病院や老人保健施設、特別養護老人ホームなどでは、理学療法士と作業療法士が一緒になって働いていることも少なくありません。しかし大半は病院で働いています。
■では、先生のご研究について教えていただけますか?
私は特に呼吸機能に関心を持ってきました。例えば、研究テーマのひとつには「体幹筋と呼吸との関連」というものがあります。体幹筋とは、文字通り体の幹となる腹部の筋や背部の筋などのことで、呼吸筋は横隔膜など呼吸に必要となる筋肉のことです。横隔膜はそもそも胸を膨らませるために活動していますが、最近では、横隔膜自体も体幹(胴体)の動きをサポートする役割があると考えられています。というのも横隔膜は胸を膨らませることで臓器を動かすだけでなく、それ自体が脊柱にも付着しています。つまり人間が動こうとするときは、体幹筋と横隔膜をうまく協調させて活動しなければならないのです。
研究では、私たちがさまざまな動作をするとき、呼吸筋や体幹筋が、どういう活動をしているのか、人はどうやってそれらをリンクさせているのかということを調べています。具体的には、体にマーカーをつけて、肩甲骨の動きや体幹(胴体)を前屈させたときの股関節の動き、脊柱の動きなどを、動く速さを変えながら調べています。さらに速く呼吸したり、ゆっくり深く息をはいたりと呼吸様式を変えることで、筋肉がどう活動をしているのかということも調べ、正常な状態と異常な状態とでは、どのように呼吸と筋肉の動くタイミングが崩れているのかを研究しています。それらを知ることで、患者さんの障害の原因を探る手がかりにし、治療に役立てる方向に持っていけたらと考えているのです。
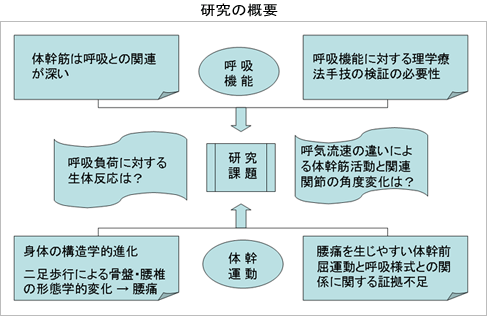
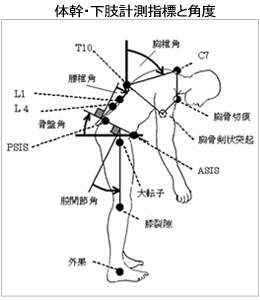
■呼吸筋と体幹筋がリンクしていると感じられる動作には、どんなものがありますか?
例えば、私たちは重いものを持つとき、息をぐっと止めて持ち上げますよね。そんなふうに息を止めると、腹腔の内圧を上げることになります。要するに、腹腔という風船を大きく膨らませるイメージです。腹筋などが働いて腹腔を膨らませると、背中の筋肉が単独でがんばらなくてもよくなり、全体の筋肉が張って、重いものを持ち上げることができます。また、そうすることで腰の筋肉の活動をいくらか軽減できるのです。ですから私たちの筋活動と呼吸とは非常に関係があり、人間にしても動物にしても、呼吸と動作が一致している状態では、効率の良いパフォーマンスが生まれるといえるのです。ただ人間は、その呼吸と動作の一致をいかようにでも意識的に崩せます。人間は二足歩行になって、体幹が自由に動くようになり、手も自由に動かせるようになりました。しかも会話をしますから、話すときに一時的に息を止めたり、吸ったりすることができます。また、話しながら歩くことも走ることもできますよね。それほど複雑なことができるのに、その一方で、本当にちょっとした動きによって腰痛を起こすことがあります。これはまだ明らかになってはいませんが、私はそうした腰痛の原因も、実は呼吸のタイミングのずれ、呼吸様式のトラブルに関連しているのではないかと考えています。今後はこの研究にも力を入れていきたいですね。
■先生が理学療法士を目指した理由とは何だったのですか?
きっかけは、ひとりの患者さんとの出会いでした。私の母の友人がリウマチで入院していて。その方に理学療法士という仕事があると紹介され、理学療法室に連れて行ってもらったのです。私は沖縄県の出身なのですが、そこにいた理学療法士の方は、当時、県内に3人しかいない理学療法士のうちのひとりでした。その方と話をして、理学療法士は貴重だから目指すべきだとアドバイスをもらったのです。それで私も「これはすごい仕事かもしれない!」と思い、目指すことにしました。この出会いがなければ、私はきっと英文科に進んでいたと思います(笑)。英語を勉強して、いつか外国に住もうかななんて考えていたので。それが全く違う方向に来てしまいました(笑)。ただ、英語は留学の際などで何かと役立っているので、学んできたことに決して無駄なものはなかったなと思っています。
■最後に、先生は本学科でどのような教育をしていきたいとお考えですか?
今は、理学療法の科学的な証拠、それが本当にどれだけ効果のあるものなのか、貢献できるものなのか求められている時代です。理学療法士を目指す若い学生たちには、単に手を差し伸べて、患者さんの動かない部分を動かしていくことだけでなく、「なぜそうしなければならないのか」という理論もきちんと構築して、把握できるような人に育ってもらわなければなりません。そういう“人”を育てることが、理学療法学科の使命だともいえます。ですから高い水準の研究をしてもらいたいと思っているんです。ただ、この分野は理論だけではなく、技術もそれに伴っていなければなりません。ですから私としては、自分のもうひとつの専門領域である“徒手的な理学療法”の学びにも力を入れていくつもりです。これは、例えば関節が硬くて動かないとか、痛みのせいである動作ができないという方に、実際に手を使って脊柱を押したり、腕を痛くないように曲げたりする治療のことです。3年生の後期からはじまる「マニュアルセラピー実習」という授業で学んでもらいます。また、この“徒手的な理学療法”の学びを定着させていき、いつかは研究ではなく、コースワーク、技術系の大学院・修士課程をつくることができないかと思っています。それが私の大きな夢ですね。
[2009年11月取材]
■医療保健学部
https://www.teu.ac.jp/gakubu/medical/index.html
看護学科
https://www.teu.ac.jp/gakubu/medical/ns/index.html
臨床工学科
https://www.teu.ac.jp/gakubu/medical/clinic/index.html
理学療法学科
https://www.teu.ac.jp/gakubu/medical/pt/index.html
作業療法学科
https://www.teu.ac.jp/gakubu/medical/ot/index.html
・次回は1月15日に配信予定です。
2009年12月4日掲出


