「臨床工学技士は、今の医療に欠かせない専門職」
医療保健学部 臨床工学科 篠原一彦 教授

■臨床工学技士とは何かというところからお話しいただけますか?
臨床工学技士は、人工心肺装置や人工呼吸器、人工心臓、人工腎臓(人工透析)などの生命維持装置の操作と保守点検を行う専門職です。例えば、心臓の手術をするとき、患者さんの心臓を外科医が手術している間の数十分間ないし1~2時間、患者さんの体内を巡る血液は、臨床工学技士が操作する人工心肺装置に流れています。つまり、手術中の患者さんの命を握っているのは、臨床工学技士であるのと言えるのです。また、もし腎臓病の患者さんが人工透析を受けることができなければ、数日から1週間ほどで生命の危機に陥ります。その命を支える人工透析の機械を操作しているのも臨床工学技士です。そう考えると臨床工学技士なしでは、今の救命医療は成り立たちません。縁の下の力持ちと思われがちですが、実は患者さんの命を直接的に背負う仕事なのです。また、個々の患者さんとの関わりだけでなく、病院内のさまざまな医療機器の安全や機能を支える役割もあります。工学的な知識と医療の知識を併せ持つのは、臨床工学技士だけと言っても過言ではありません。国家資格としては始まって23年と若く、社会的にも看護師やリハビリ系の資格に比べると、まだ知られていませんが、これからどんどんその数は増えていくはずです。
■活躍の場としては、どういうところが考えられますか?
ひとつは、病院が挙げられます。仕事内容は、先に言いました生命維持装置の操作と保守点検。それから病院全体の医療機器の安全管理や医師・看護士・医療スタッフに医療機器の安全な使い方を指導するといった教育。さらには、まだごく一部ですが病院全体の医療機器購入など、経営に携わる部分まで担う臨床工学技士もいます。また、新しい医薬品や医療機器の安全性を審査する厚生労働省の機関でも、臨床工学技士は必要とされています。そこではこれまで薬剤師が中心となって新薬や医療機器の審査を行ってきました。しかし、今は医療機器の専門職である臨床工学技士の力が求められているのです。ほかにも医療機器メーカーでの研究開発や、医療従事者向けに用意されている医療機器の操作のトレーニング施設などでも活躍しています。このように臨床工学技士の働く場所はとても幅広く、今後も日に日に拡大していくだろうと予想されます。
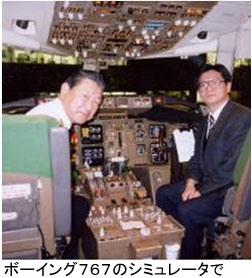
■では、先生のご研究について教えてください。
ひとつは、いわゆる人間工学の分野にあたる医療安全や産業安全に関する研究があります。航空運航システム研究会という大手航空2社と空・海・陸の自衛隊、心理学者、工学者、法学者などが集まった学際的な研究会で、航空の安全についてさまざまな研究をしています。また、そこで得たことは医療安全へとフィードバックしています。例えば、使いやすい医療機器の設計や間違いにくい薬の表示方法なども研究に含まれています。これらの研究は、今後、臨床工学科の教育や学生たちの卒業研究にも反映していくつもりです。

それから、私は消化器を専門とする外科医ですから、使いやすく、痛くない内視鏡の研究にも取り組んでいます。今の胃カメラや大腸カメラは、医師の腕に頼るところ多分にあります。カプセル内視鏡もありますが、飲んでから腸の流れにあわせて動くため、外に出てくるまでに20数時間もかかり、ポリープなどを切除することはできません。やはり口、鼻、あるいはお尻からカメラを入れて胃腸の中を見て、軽い病気ならその場で切除するという方法が欠かせないのです。ですから、患者さんに負担が少なく、誰にでもやさしく使える内視鏡を開発しようと、地域メーカーと一緒になって取り組んでいます。
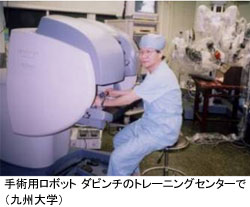
さらに、日本の医療機器産業の活性化や、すぐに役立つような医療機器の開発から販売までをつなぐお手伝いもしています。日本の医療機器、特に人工関節やペースメーカーなどは、100%輸入に頼っています。これは日本の技術や研究が後進だからではありません。ペースメーカーは、今の学生さんたちが幼い頃に買ってもらったテレビゲームよりもはるかにレベルの低いコンピュータで動きます。それでも日本製のペースメーカーはありません。その理由のひとつは、厚生労働省の規制が大きいこと。そしてもうひとつは、コンピュータや電池、電線をつくっている日本のメーカーが、万一、開発した医療機器に不具合があった場合、非常に大きなリスクを背負うことになると考えているからです。そういうわけで、日本では欧米からペースメーカーを輸入し、結果的に120万~150万円という高値で販売されるに至っています。ですから私は、経済産業省やいくつかの学会を手伝いながら、まずは、ものづくりをがんばっている地域の企業や中小企業が医療機器に参入しやすいように法律を変えようと取り組んでいます。また、ガイドブックをつくったり、関東の国立大学などで医工連携・産学連携のフォーラムを開催したりして、日本の医療機器産業の活性化をはかるお手伝いをしているのです。医療機器は、腕の良い職人さんと知恵のある工学者が集まればつくることができます。それをつなげていくのが、大学の役割のひとつだと考えているのです。
■外科医である先生が、臨床工学や人間工学に関わったきっかけと何だったのですか?
もともと私は文系人間なので、実は理数系のセンスも興味もないんです(笑)。ただ、昔から鉄道や飛行機などの乗り物は大好きでした。だから医者になって5年目くらいから、独学で心理学や安全についての勉強をはじめたのです。そんな私が10年ほど前に、たまたま工学系の先生方と手術用ロボットの開発を手がける機会があって。そのときに、いわゆる“ものの使い勝手”とか“人間の行動”を生産工学の手法を用いて解析したのです。それが工学系の先生方に評価されて、今に至るという感じです。非常に職人芸的な医学と、定量的にものを扱う工学との橋渡し役として、工学系の先生方と共に研究をしてきました。
■最後に今後の展望をお聞かせください。
いよいよ2010年の4月から、蒲田の地で医療保健学部とデザイン学部がスタートします。その中で私は、デザイン学部と医療保健学部の学生同士が交流してくれることを期待しています。ですから今、私が問題意識を持っているのは、新しいキャンパスで新しいサークルをどうつくっていくかということなのです。というのも大学時代にサークル活動を通して、一生付き合える友人を得ることは、とても大切だからです。私の場合、大学時代のサークル活動での経験や人脈が、今になってものすごく生きてきています。私だけでなく、多くの人がそう感じているはずです。同じ学部の友人や先輩・後輩は卒業後も同じ医療従事者という専門職に就きます。だからこそ困ったときに仕事のこと、新しい人材が欲しいというようなことも相談できるのです。また、自分の専門分野しか見えない視野の狭い学生にならないためにも、ぜひ他学部の学生と交流してほしいと思っています。そのフレームワークをつくっていくことが、新キャンパスで教える教員としての私の責務です。
[2009年12月取材]
■医療保健学部
https://www.teu.ac.jp/gakubu/medical/index.html
看護学科
https://www.teu.ac.jp/gakubu/medical/ns/index.html
臨床工学科
https://www.teu.ac.jp/gakubu/medical/clinic/index.html
理学療法学科
https://www.teu.ac.jp/gakubu/medical/pt/index.html
作業療法学科
https://www.teu.ac.jp/gakubu/medical/ot/index.html
・次回は2月12日に配信予定です。
2010年1月8日掲出


